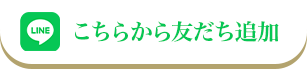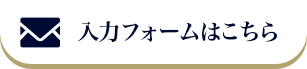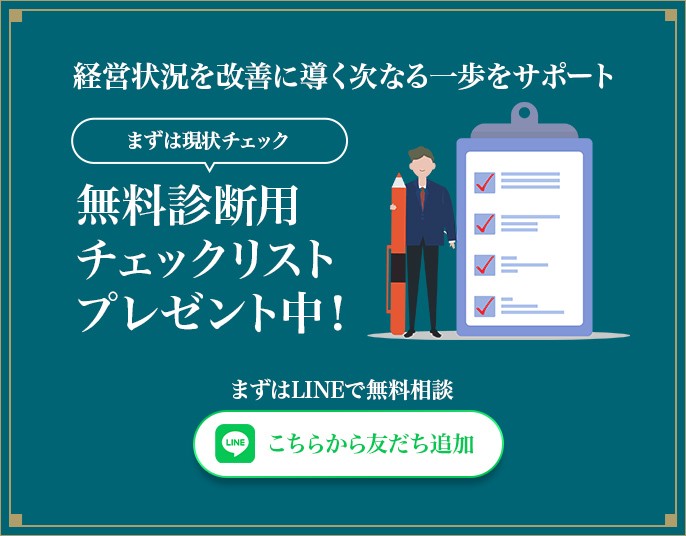中小企業診断士が事業承継について基礎知識から応用まで徹底解説!

事業承継は、中小企業にとって避けて通れない重要なテーマです。
とくに日本では、中小企業が多数存在し、経営者の高齢化が進んでいるため、事業承継が重要な課題となっています。
事業を次世代に引き継ぐ際のプロセスや手法を理解することで、企業の存続と発展を確保することができるといえるでしょう。
本記事では、中小企業診断士の視点から、そんな事業承継の基礎知識から応用までを徹底解説します。
この記事はこんな人にオススメ!
- 事業継承を検討している企業の経営者
- 事業承継の方法について知りたい方
- 事業承継に関する知識を得たい方
- 事業承継の成功例とリスクについてしっかりと知りたい方
- 事業承継の専門家をつけようか悩んでいる事業者
事業承継とは

事業承継(ビジネス・サクセッション)は、企業や事業の経営を次世代に引き継ぐプロセスです。
これには、経営権や株式、資産の移転だけでなく、企業文化や経営理念の継承も含まれます。
事業承継には、内部承継(家族や従業員への引き継ぎ)と外部承継(第三者への売却や合併)があります。
どちらの方法を選ぶかは、企業の状況や経営者の意向によって異なります。
事業承継は企業の存続と成長にとって重要なステップであり、計画的かつ慎重に進めることが求められます。
事業承継の重要性
事業承継は企業の将来に直結する重要な課題です。
特に中小企業においては、経営者の高齢化が進む中で適切な事業承継ができないと、事業の存続が危ぶまれます。
事業承継がうまくいくと、企業の安定的な成長が期待でき、従業員や取引先との信頼関係も維持されます。
また、後継者が経営に携わることで、新たな視点や革新的なアイデアが導入される可能性も高まります。
一方で、事業承継が滞ると、経営の混乱や事業の縮小、最悪の場合には廃業のリスクが生じます。
そのため、事業承継の計画と実行は経営者の重要な責務と言えます。
事業承継の流れについて

事業承継のプロセスは、後継者の選定、承継計画の策定、税務対策など、多岐にわたります。
計画的に進めることで、リスクを最小限に抑えることができます。
以下にそのステップを簡単に3つに分けて紹介します。
- 現状確認(経営状況の確認)
- 事業を後継者に円滑に引き渡すためには、経営状況や課題、資源などを可視化し、正確に把握することが重要です。
専門家の助けを借りて、正確な情報を把握しておくことが求められます。
これらのデータは企業の価値に直接関わるため、非常に重要です。
- 経営改善(磨き上げ)
- 経営者は、事業を後継者に引き渡す前に経営改善に努め、事業を最適な状態に整えておくことが望まれます。
事業承継の前に経営改善に取り組み、事業を最大限に磨き上げることで、後継者にとって引き継ぎたいと思わせる魅力的な状態にします。
- 事業承継の実行
- 把握した課題を解消しながら、事業承継計画やM&A手続きに従って進めていきます。
親族内承継、従業員承継、またはM&Aのいずれの方法を選ぶ場合でも、実行時には税務や法務などの専門知識が必要です。
そのため、専門家と協力して進めることが推奨されます。
事業承継の種類は?
一言で事業承継といっても、その種類は大きく三つに分けられます。
ここではそれぞれの方法について紹介していきます。
①親族内承継
親族内承継は、経営者の子供や親族に事業を引き継ぐ方法です。家族内での引き継ぎが主となります。
②従業員承継
従業員承継は、企業内部の従業員に事業を引き継ぐ方法です。特に役員や幹部社員が後継者となることが多いです。
③M&A(企業買収・合併)
M&Aは、外部の企業や個人に事業を売却する方法です。
第三者に引き継ぐ形になります。
M&Aとは、企業の合併(Mergers)や買収(Acquisitions)を指します。
これは、企業が他の企業を統合することで規模や競争力を拡大しようとする戦略の一つです。
具体的には以下のような形態があります。
合併(Mergers): 二つ以上の企業が一つの企業に統合されることを指します。通常、合併後の企業は合併前の企業の資産や負債を引き継ぎます。
買収(Acquisitions): 一つの企業が他の企業の株式や資産を取得し、経営権を掌握することを指します。買収には友好的なもの(友好的買収)と敵対的なもの(敵対的買収)があります。
M&Aは、企業が市場シェアを拡大したり、新しい市場に進出したり、技術やノウハウを取得したりするための効果的な手段とされています。
しかし、成功するためには適切な戦略と計画、そしてしっかりとしたデューデリジェンスが不可欠です。
M&Aの主な目的
市場シェアの拡大: 同業他社との統合によって市場シェアを増やすことができます。
新市場への進出: 他の地域や国に拠点を持つ企業を買収することで、新市場に迅速に進出することができます。
コスト削減: 経済規模の拡大により、コストの削減や効率化が可能になります。
技術やノウハウの取得: 買収対象企業が持つ特許、技術、専門知識を取得することができます。
多角化: 事業ポートフォリオを多様化し、リスクを分散することができます。
M&Aを成功させるためには、綿密な計画と慎重な実行が求められます。また、統合後の組織文化の調整や従業員の適応も重要な要素となります。
それぞれの手法には一長一短がありますので、企業の状況や経営者のビジョンに基づいて、適切な方法を選択することが重要です。
専門家の助言を得ながら、計画的に進めることが成功の鍵となります。
事業承継の事例について

ここまで事業承継について基礎知識を紹介してきました。
事業承継がどのようなものなのか、皆さんおわかりいただけたと思います。
では実際にどのようなケースがあるのでしょうか。
ここからは事業承継の事例を3つ紹介したいと思います。
中村屋の例
まず、中村屋の事例について紹介します。
中村屋は創業100年以上の老舗和菓子店であり、創業者の孫にあたる中村幸次郎氏が事業を引き継ぎました。
事業承継により新しい経営体制が整い、さらに発展を遂げました。
具体的な施策としては、伝統的な製法を守りつつ、新商品の開発やパッケージデザインの刷新を行いました。
新たな顧客層開拓としてはインターネットを活用した販売チャネルの拡大に注力しました。
その成果として、新たな市場の開拓とオンライン販売の強化により売上が増加することに繋がりました。
サントリーとビーム・サントリーの例
サントリーは、日本の大手飲料メーカーであり、グローバルに展開している企業です。
2014年に、サントリーはアメリカのアルコール飲料メーカーであるビーム社(Beam Inc.)を買収し、ビーム・サントリーを設立しました。
このM&Aは、サントリーが事業承継の一環として、ビーム社の持つブランドや市場シェアを取り込むことを目的としました。
サントリーの創業者が引退し、事業承継を迎える中で、グローバル展開を強化するための戦略としてビーム・サントリーの設立が選ばれました。
ビーム社の買収により、サントリーはウイスキーを中心とするアルコール市場での競争力を強化し、世界的なブランドポートフォリオを拡充しました。
このM&Aにより、サントリーは国際的なプレゼンスを大幅に向上させ、事業承継を成功させました。
鈴木株式会社の事例
最後に、スズキ株式会社の事例について紹介します。
スズキ株式会社では、長年にわたり鈴木修氏が経営を担ってきましたが、2015年に息子の鈴木俊宏氏に社長職を引き継ぎました。
具体的な施策としては、インド市場を中心にアジア各国での事業拡大を図りました。
また、電動化や自動運転技術の開発に積極的に取り組み、小型車やエコカーのラインナップを強化することによって、環境に優しい製品を提供しました。
結果として、インド市場での成功により売上と利益が大幅に増加することに繋がりました。
事業承継の応用!?

ここまでは基本的な事業承継を事例をもと紹介しましたが、ここからは事業承継の珍しい応用方法をいくつか紹介します。
ここで一般的な事業承継の枠を超えたユニークなアプローチがあります。
地域コミュニティによる事業承継
1つ目に地域コミュニティ全体が協力して企業の事業を承継するという珍しいケースがあります。
例えば、ある小さな町の老舗の製造業者が廃業の危機に直面した際、町の住民や地方自治体が共同で資金を出し合い、企業を買収しました。
地域の住民は、その企業が地域経済や文化にとって重要であると考え、共同で運営を引き継ぐことで事業を維持しました。
このように地域全体が企業の存続に関与することは、事業承継のユニークな形の1つです。
【事例】アニマルシェルターと地域コミュニティの支援
あるアメリカのアニマルシェルターが、運営の存続が危ぶまれる中、地域コミュニティからの支援を受けて事業承継を行いました。
地域コミュニティが積極的に関与し、運営の改善と資金調達を支援することで、シェルターは存続し続けることができました。この事例は、地域社会が事業承継に積極的に関与し、事業の継続性を確保した珍しいケースです。
クラウドファンディングによる事業承継

1つ目はクラウドファンディングを利用して、企業の事業承継を行う方法です。
クラウドファンディングを利用した事業承継の具体例として、「セント・アンドリューズ・カフェ」の事例があります。
この東京都内の老舗カフェは、高齢の経営者が後継者不在で経営難に直面していました。
地域にとって重要な存在だったため、閉店を避けたいと考え、クラウドファンディングで資金調達を行うことに決めました。
クラウドファンディングプラットフォームを利用して1,000万円の目標額を設定し、支援者には特製ドリンクの引換券や試食イベントへの招待、支援者名簿の設置などのリターンを用意しました。
キャンペーンは成功し、目標額を超える1,200万円が集まりました。
この資金で地域の若手起業家に経営権を譲渡し、店舗のリニューアルや新メニューの導入を行いました。
結果的に、カフェは地域の支援を受けて存続し、新しい経営者のもとで人気が再び高まりました。
この事例は、クラウドファンディングを使って事業承継を成功させた良い例です。
トム・フォードとファッション業界
最後にトム・フォードの例を挙げて珍しい事業承継のケースを紹介したいと思います。
トム・フォードは、ファッションデザイナーとして知られる人物であり、彼のデザインブランド「トム・フォード」は、彼の個人的なブランドとしてスタートしました。
2016年に、トム・フォードは自らのブランドをコフロン(Kering)というフランスのファッショングループに売却しました。
この売却により、トム・フォードはデザインのクリエイティブディレクションに専念し、経営はコフロンに引き継がれました。
この事例は、著名なデザイナーが自身のブランドをグローバルなファッショングループに譲渡し、クリエイティブな役割に専念するという珍しい事業承継の形です。
このように事業承継はその業態によって様々なケースがあります。
自分の場合はどのような事業承継が望ましいかは専門家の意見を参考にするといいでしょう。
まとめ
事業承継は、企業の存続と発展にとって極めて重要なプロセスです。
計画的に準備を進め、専門家の助言を受けながら進めることで、リスクを最小限に抑え、成功に導くことができます。
当社では専門家による事業承継のサポート業務を行っております。
皆さんも是非これを機に一度相談してみてはいかがでしょうか。
当社の強み
トリガーコンサルティングではM&A・事業承継のサポートを行っております。
・事業承継実績は100件越え
・中小企業診断士として専門知識と多くの事例に基づく経験
・各専門家と協力し、財務・法務・税務の各分野にわたる包括的なサポート
M&Aや事業承継にお困りの企業様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
詳細は以下のページからご確認ください。