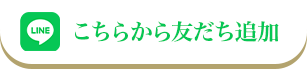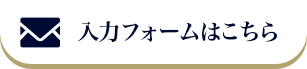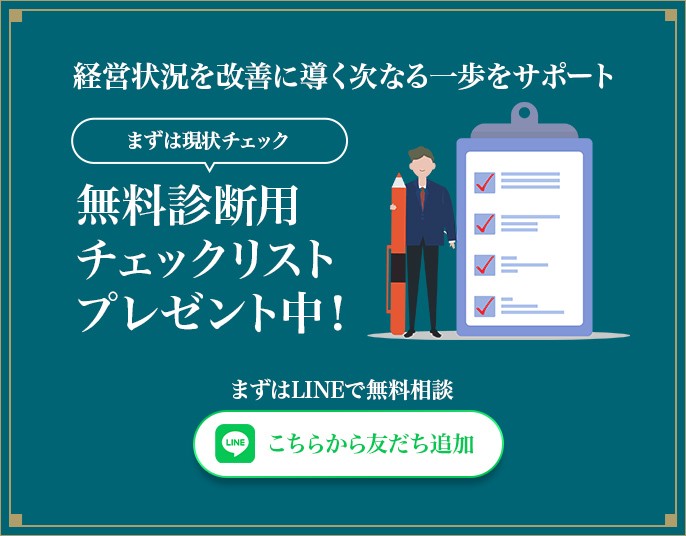【図解でわかる】事業承継とM&Aの違いや、それぞれのポイントを徹底解説!

みなさんは、事業承継とM&Aの違いわかりますか?
事業承継とM&Aは、どちらも企業の未来を形作る重要な選択肢です。
どちらも企業の存続と成長を目的としていますが、アプローチや手法に大きな違いがあります。
本記事では、事業承継・M&Aの説明や、事業承継とM&Aの違い、失敗しないためのポイントなどについて
図などを用いながら詳しく解説していきたいと思います。
事業承継を考えている事業者様や事業承継について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事はこんな人におススメ
- 事業承継をしようとしているしている中小企業
- M&Aをしようとしているしている中小企業
- 会社の後継者がいない
- 廃業したくない中小企業
- 従業員やノウハウを後世に継がせたい
事業承継について

まず最初に事業承継についてお話ししていきたいと思います。
内容としては、
・データで見る日本と事業承継の現状
・事業承継とは
・事業承継の種類
上記の3点から、1つずつ説明していきたいと思います。
データで見る日本と事業承継の現状
経営者の高齢化
経営者年齢は平均60.5歳
過去最高を更新
高齢の経営者における後継者不在率も改善してはいるが依然として高い水準


後継者不足と廃業
休廃業・解散件数は新型コロナウイルス感染症の影響も相待って増加傾向
2023年における廃業理由の約3割が後継者難
によるもの


事業承継を契機とした成長
事業承継後3年目以降からは
売上高成長率が同業種平均を上回る
事業承継時の経営者年齢が若い企業ほど、
事業再構築に取り組む傾向にある


近年、中小企業の経営者の高齢化に拍車がかかっており、経営者年齢のピークはこの20年間で50代から60~70代へと大きく上昇しています。
また、後継者の不在状況はかなり深刻な状況になってきており、近年増加する中小企業の廃業の大きな要因の一つになっています。
その点、事業承継による世代交代やM&Aによる会社の規模拡大は企業の成長に効果的です。
今後の経営が困難なものになってきたと感じることがあれば、倒産という選択肢を取る前に、事業承継などを一度検討してみるのもいいでしょう。
事業承継とは

ここからは、事業承継についてお話ししていきたいと思います。
まず、事業承継とは、「会社の経営を現在の経営者から別の後継者へと引き継ぐこと」という意味を持ちます。
上場企業などの大企業では、所有と経営が分離されており、株式を保有する株主が社長などの取締役に経営を委任しています。
そのため、社長が変わっても、経営の分離が進んでいるため、経営陣の交代は比較的スムーズに行われます。
しかし、中小企業などでは、オーナー経営者の手腕や人柄がその会社の強みや社風などとなっていることも多いため、後継者が誰になるかというのは極めて重要になってきます。
なので、慎重に検討して選ぶ必要があると考えます。
事業承継の種類

次に、事業承継の種類のお話に入っていきます。
事業承継は、引き継ぐ先によって、親族内承継、従業員承継、M&A(社外への引継ぎ)に分類されます。
この章では、図に表しながら、1つずつ詳しくみていきたいと思います。
では早速、親族内承継から見ていきましょう!
親族内承継

相続などの観点からも、最も望ましいのが子息等の親族への事業承継です。
この親族内承継ですが、20年以上前であれば、この子息等の親族への承継が事業承継全体の9割以上を占めていましたが、日本全国における、後継者不足によって親族への承継は減っており、現在では、全体の6割を切ってしまっています。
後継者不足の主な理由としては、高校を卒業したら大学に進学するというのが一般的になった結果、親が会社を経営していても、子息は大学卒業後に大手企業・中小企業などといった他の業種・企業に就職したり、医師や弁護士、公認会計士といった専門職に就くなどといった、親の会社の後を継ぐことを前提としない人生を歩むケースが増加したことが挙げられるでしょう。
経営者である親が子息に継いでもらう考え前提でいたとしても、親の苦労を近くで見てきた過去がることなどを考えると、子息本人には全くその気がなくなってしまったというのはよくある話ではあります。
親族外承継

前述した、子息等の親族への事業承継が何かしらの理由でできない場合、次に候補として挙がるのが自社役員・社員への承継です。
ですが、この選択肢は主に資金面での、かなり困難な選択肢となる場合があります。
こう述べた理由としては、黒字企業で無借金経営の場合、譲渡価格が高額になってしまうため、後継者にとって購入代金の調達が非常に難しくなるといった側面があるためです。
一方で、借入金の大きな企業の場合、譲渡価格は比較的低く抑えることができますが、借入の連帯保証や担保提供などで不足が生じるのが一般的で、仮に連帯保証や担保提供の能力があったとしても、後継者候補にその部分を背負う覚悟がなく、結果として断念してしまうケースがかなり多くあります。
つまり結論として、自社役員・社員への承継というのは、よほど資産を持った人がいなければ難しいという結論になります。
また、仮にそのような役員・社員が社内に在籍していたとしても、そもそも、その人にこの会社をやっていける経営能力があるかという問題も新たに発生してきます。
部下としては非常に優秀であっても、経営者として優秀かどうかはわからないかと思います。
冷静に社内で考えた結果、後継者として任せられないと、事業承継を諦めるケースも多いようです。
M&A

子息等の親族や親族外の自社役員・社員への事業承継ができない場合、残る選択肢は、第三者企業への事業承継(M&A)となってきます。
M&Aによる第三者企業への事業承継では、従業員の雇用や取引との取引関係を今まで通り維持できるのはもちろん、売り手側と買い手側の双方の資本や人材、ノウハウ、販路を活用して、両者をより大きく発展させることができる可能性を秘めているものとなっています。
海外では主流になってきてはいますが、日本では、まだまだ社外の第三者へ会社を譲ることに抵抗感があり、身内に事業承継できない場合は「廃業」を選択する経営者も多いようです。
ですが、「廃業」を選択すると、従業員は、働き口を失ってしまい、取引先にも多大な影響をかけてしまいます。
また、第三者への事業承継は、「廃業」と比べて、日本経済にも圧倒的な利益をもたらす引退方法であるため、中小企業庁もM&Aによる事業承継を推進しており、中小企業におけるM&Aの実施件数は年々増加傾向にあります。
その一方、完全に外部の方に自社を継承するので、上記で説明した「親族内継承」「親族外継承」よりも多少リスクがあるのもまた事実です。
なので、M&Aする際には、しっかりと相手企業とコミュニケーションをとり、すべての項目で思いが合致した場合、M&Aをすると良いでしょう。
M&Aについて

ここまでは、事業承継についてのお話でしたが、ここからは、M&Aについて説明していきたいと思います。
M&Aとは


M&Aとは、「Mergers & Acquisitions」の略であり、企業の合併や買収を指します。
企業が他の企業を買収したり、二つ以上の企業が合併して新しい企業体を形成する行為を含みます。
企業の成長戦略として重要な手段であり、競争力の強化、事業拡大、新規市場参入などを目的として行われます。
M&Aというとマイナスイメージもありますが、それは一部の極端なケースであり、大多数のケースでは、円満な関係で終わっています。

上記の図でもわかるように、近年、M&Aの実施件数は年々伸び続けています。
事業承継を考えている企業様は、是非、M&Aも選択肢の1つに加えてみてはいかがでしょうか。
事業承継とM&Aの違い

ここでは、事業承継とM&Aの違いについてお話ししていきます。
上記で解説したものを見た方の中にはお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
M&Aは事業承継の手段の1つです。
事業が他人の手に渡るという点では共通していますが、
それが経営者の引退によるものかどうかで違いが見られます。
なので、違いというよりは、事業承継の中にある数ある中の選択肢のうちの1つと思ってください。

事業承継で失敗しないためのポイント

最後に事業承継において、失敗しないポイントを3つほどご紹介したいと思います。
ポイントは下記の3つです。
・早期準備と計画
・適切な選定と育成
・専門家などへの相談
それでは、1つずつ解説していきたいと思います。
早期準備と計画
事業承継には、後継者の選定や後継者の育成・教育、業務の引継ぎなど、実行までに平均して10年程度を要すると言われている、とても長いものになります。
まずは、経営者として、事業承継に向けた準備の重要性を十分に認識すること、そして、平均引退年齢が 70 歳前後であること、事業継承に平均10年を要することなどを踏まえて、60 歳頃には最低でも事業承継に向けた準備に着手することがポイントとなってきます。
なので、早め早めの行動を取るようにしましょう。
適切な選定と育成
事業承継の成功には、適任の後継者を見つけ出し、しっかりと育成することが不可欠です。
まず、後継者を選定する際には、選定基準を明確にすることが重要です。経営能力や戦略的思考、問題解決能力、リーダーシップスキルなど、経営に必要な能力を持っているかどうかが問われます。
また、企業の将来をどのように見据えているか、企業の方向性に合致するビジョンを持っているかも重要な要素になってくるのでしっかり見るようにしましょう。
さらに、企業の価値観や文化を理解し、尊重できるかどうか、信頼性や誠実さ、対人関係のスキルなど、人間性の面でも適任であるかも評価すると良いでしょう。
そして、同時に育成も大事になってきます。
後継者の育成には、計画的なプログラムが必要です。
まず、具体的な育成目標を設定し、何を達成するべきかを明確にします。
その上で、経営スキルやリーダーシップの訓練プログラムを設け、後継者に必要な知識とスキルを習得させましょう。
また、現場での実務経験を通じて、実践的なスキルを身につけさせることも重要です。
専門家などへの相談
事業承継の諸々は分かってはいるものの、初めてのことで何から手を付けていいのか分からないものかと思います。
その際は、まず、顧問の公認会計士・税理士や取引金融機関、公的支援機関など、信頼の置ける相手に相談してみるのが一番いいでしょう。親族や役員・社員への承継を漠然と考えている場合であれば、親族や後継者候補自身と話をしてみることも重要なことの1つです。
また、後継者が未定である、あるいは不在であるという場合であれば、弊社をはじめとした民間の事業継承・M&Aサポート会社や各都道府県に設置されている事業引継ぎ支援センターに相談してみるのも良いでしょう。
以上のように、事業承継に取り組んでいくにあたっては、とにかく「早めの相談」がポイントです。
とりあえず、まずは信頼の置ける相手に相談してみましょう。
まとめ
今回の記事では、「【図解でわかる】事業承継とM&Aの違いや、それぞれのポイントを徹底解説!」と題して、事業承継・M&Aの説明や、事業承継とM&Aの違い、失敗しないためのポイントなどについて、図などを用いながら詳しく解説してきました。
内容としては、
・事業承継について
・M&Aについて
・事業承継とM&Aの違い
・事業承継で失敗しないためのポイント
について解説しました。
本記事が、事業承継を考えている事業者様や事業承継について詳しく知りたい方の助けになれば幸いです。
今回も最後まで閲覧いただきありがとうございました。
下記に類似した記事も貼っていますので、是非そちらもご覧ください。



当社の強み
トリガーコンサルティングではM&A・事業承継のサポートを行っております。
・事業承継実績は100件越え
・中小企業診断士として専門知識と多くの事例に基づく経験
・各専門家と協力し、財務・法務・税務の各分野にわたる包括的なサポート
M&Aや事業承継にお困りの企業様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
詳細は以下のページからご確認ください。